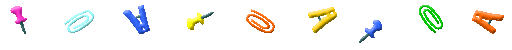
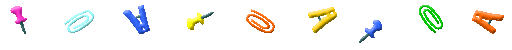
美月・入学準備編 その1
「H台小学校・入学」
正式に就学通知が来てから、あちこちに電話・連絡をして、落ち着きも覚めやらぬ翌週、3月2日。
早々に、市教委の方と、打ち合わせが行われることになった。
粘り抜いて、皆さんの援助の結果、新設される『肢体不自由学級』 喜びはつかの間。何からどうすればいいのか、何を誰にどう要求すればいいのか・・・ また手探りてさぐり・・・
とにかく、「肢体学級」の最小限の知識を付け焼刃で仕入れ、当日の打ち合わせに向かう。
3月2日 「事後、打ち合わせ」 於 小学校校長室
主に、教室・設備等について
![]() 肢体不自由学級、ということで、教室の仕様など概ねの規定があるものの、新年度にあたっては準備に間に合わないこともあるので、了承してください、と言われた。
肢体不自由学級、ということで、教室の仕様など概ねの規定があるものの、新年度にあたっては準備に間に合わないこともあるので、了承してください、と言われた。
![]() 教室は、仕様として半分をたたみ・カーペット敷き。ベッドをおいたり、たたみの一部を高くすることも可能。ベッド周りは、カーテンをつける。 などが概ねの仕様。
教室は、仕様として半分をたたみ・カーペット敷き。ベッドをおいたり、たたみの一部を高くすることも可能。ベッド周りは、カーテンをつける。 などが概ねの仕様。
それ以外のマット・クッションについては、予算の範囲内で、新学期以降・購入。あるいは、持込。
![]() 給湯設備も仕様に含まれるが、一般教室を改造する場合、工事が難しく、新年度には間に合わない可能性がある。(この時点では、どこの教室に入るか不明だった)
給湯設備も仕様に含まれるが、一般教室を改造する場合、工事が難しく、新年度には間に合わない可能性がある。(この時点では、どこの教室に入るか不明だった)
レンジ・コンロ・冷蔵庫ナドも持ち込みはOK
![]() トイレについて。
トイレについて。
身障者用のトイレは学校に既存であるものの、改造は難しい。 養護学校にあるような、長洋式が介助しやすいものの、普通校では、『一人だけのための改造』ということになると、イロイロな方面から苦情が来る・・・んだそう。 長洋式とは、二人掛けで後ろから介助しやすいようになっている、長四角になったトイレ。これにすると、他の人が使えない、という理屈。・・・・本当に?!
トイレットチェアを持ち込むか、便器を改造しない方法を考えるように・・・ということになった。
![]() 空調設備。
空調設備。
暖房は既存であるものの、冷房設備は、16年度の予算編成は終わっているので、つけられない可能性がある。 体温管理の必要性を、もう一度説明したものの、確たる返事は難しいとの事。
夏は学校を休め、ということか・・・
![]() ミキサー
ミキサー
コレが思いもよらぬ伏兵だった。
曰く、「市教委としては普通校では、ミキサーの使用は認可できない」 と言う。しかし、使わないと、給食は食べられませんが?
「そのような子供のために、養護学校で様々な形態に対応した食事を提供している」 はあ? しかし、もうここに、就学が決まった以上、ミキサーを使わないと、給食食べられませんが? 他校で使っているところもあるし・・・。
「衛生面での問題や、管理の問題があって、難しいということ。O-157などが起こったとき、原因の特定が難しくなる。市側としては、そういう判断。後は、学校長の判断でやってもらうしかない」
・・・・ 養護学校で認められていて、地域校ではできない。 このフレーズが後々も様々な問題に関連していく。
![]() 自宅からの持込
自宅からの持込
美月個人的に使うものは、持込することになった。
・座位保持椅子
・タオル・マット類
・その他、1年生で使うもの (お道具箱・粘土・算数セット・上靴・など)
入学以降揃えたもの
・書面台
・冷風扇風機
・三角マット
・体操服
・鍵盤ハーモニカ
![]() その他
その他
教室内に必要なものは、順次新学期以降、学校側が揃えていくとのこと。内装については、春休みを利用して改装。
揃えていくものの予定としては
・ボールプール
・トランポリン
・セラピーボール
・パソコン関連(ビッグマック・マウスなど)
天井を利用する感覚遊具は、難しいとこのこと。なぜか? 3年後に予定されている『特別支援教育制度』が予定されていて、そうなると、肢体不自由児の部屋などなくなるから、部屋の大改造は控えておくように、だそうだ。 あっさりと目の前でそう言い切られるのも、唖然・・・
プロムボードは、短下肢装具装着や時間的な問題もあって、持ち込みは不可。
![]() 校長室での話が終わった後、学校長同伴で、予定されている教室や設備をを見に行く。
校長室での話が終わった後、学校長同伴で、予定されている教室や設備をを見に行く。
なんと、教室は現在会議室として使っている部屋を使用するとの事。
ラッキーなことに、ここはカーペット敷き。給湯設備、冷蔵庫有り。冷暖房空調設備あり、の部屋なのだ。校長先生はこともなげに、「ここが一番いいでしょう。一階だし」
市教委がわも「あ、そうですね」 なら、はじめから打ち合わせしといてください!!
ミキサーの件もいい機会なので、三者が揃っている場で直接校長先生に聞いてみる。
「え?いいんじゃないんですか?」
また、市側の説明を延々聞く羽目になった。校長先生は即答を避けていたけれど、感触としては問題なさそう。
次回は春休み頃に、入学以降からの生活・教育面のことの話をするとして、この日の打ち合わせは終わった。
![]()
3月9日 「Y小学校・肢体不自由クラス見学」
順番が逆かもしれない、と思いつつも実際の現場を見てみたく、この時期になってから二つお隣の校区のY小学校へ見学にいくことになった。
百聞は一見にしかず。 まさにそのとおり。
EVや、トイレの設備。また、教室でのKくんの居場所。お友達とのかかわり。交流での様子。
まさに、まさに「学校生活」だった。ゆったり時間の流れる療育園生活風景とは一変!!なのだ。時間の区切りが早く、移動もトイレも秒速で進んでいる・・・と思えるほど。
子供たちの声があっちこっちから降ってくる。正直、ちょっとやっていけるのか、心配になった。しかし、みんな生き生きしている。慣れていけばなんとかなるんだろうか・・・それにしても、頭で描いているだけでは、わからないことの方が多いもんだと実感。
色々写真も撮らせていただき、交流クラスへの参加・果ては給食時間もご一緒させていただいた。
限りある時間の中でのことだったけれど、どんなに大きな収穫になったか計り知れない。
お忙しい時間だったのに、親切に対応していただいたY小学校の先生方、またKくんのお母さん。いきなりの訪問でお手間をとらせました。どうもありがとうございました。(W園のS田先生、中継ぎありがとう)
なかよしのクラスのお友達が「明日も来る?」「一年生で来る?」「来たらいいのに・・・」と言ってくれたこと、とてもせつなく、うれしかったです。
![]()
4月5日 「F岡先生より電話。担任が決まる」
4月6日 「入学に向けての打ち合わせ」 於 小学校校長室
春休みもあと少し・・・のところへ、電話があった。担任をしていただくことになるF岡先生からだった。
就学時検診の時もいらっしゃったし、もしかしたら・・・と言う気がしていたけれど、予想通りとなった。ありがたい。これで前途はとても見通しのよいものになった。 後日実感していくのだけれど、直接関わっていく現場の先生方の力量というのはとても大きい。 養護経験の豊富な先生がいる時期に入学できるというのは、めぐり合わせがよかったとはいえ、これもミツキのもって生まれた幸運というしかない。
![]() 入学後の予定について
入学後の予定について
・入学当初はミツキと一緒に付き添うこと
・4月終わりから給食スタート
→摂食は保護者が行うこと(これは、しばらくの間。というつもりだったけれど・・・ 現在も続いている。様々な問題があり)
・トイレは、学校生活の一環として、先生が介助に行くこと
・5月頃までは、学校内での生活に慣れること
などが話し合われた。以降は、入学後の様子をみながら対処ということになった。(授業の内容や、交流の状態など)
![]() ミキサー
ミキサー
担任の先生と校長先生がいるところで、再度問い合わせる。
使用をしなくては、給食は食べられない。こちらとしても、そのあたりはわかってもらわなくては・・・ 必死
使用に関しては、あっさりOK。でも、教室で保護者が調理・管理という条件で。 もちろん意義なし。
というところで、ミキサー持込決定。
献立表をみて、食べにくそうな日には、家から持ち込みをしてもいいということになった。
後日、電子レンジを学校側が購入してくれることになり、これで食事面のシンパイは当面なくなった。
![]()
入学式は4月8日 あと二日にせまってきていました。いよいよ小学生生活スタートです。